Uncategorized

2024.07.17
ライフジャケットを使った安全教育

2024.07.10
夏季休業中のすまいるスクール仕出し弁当【全施設で実施】
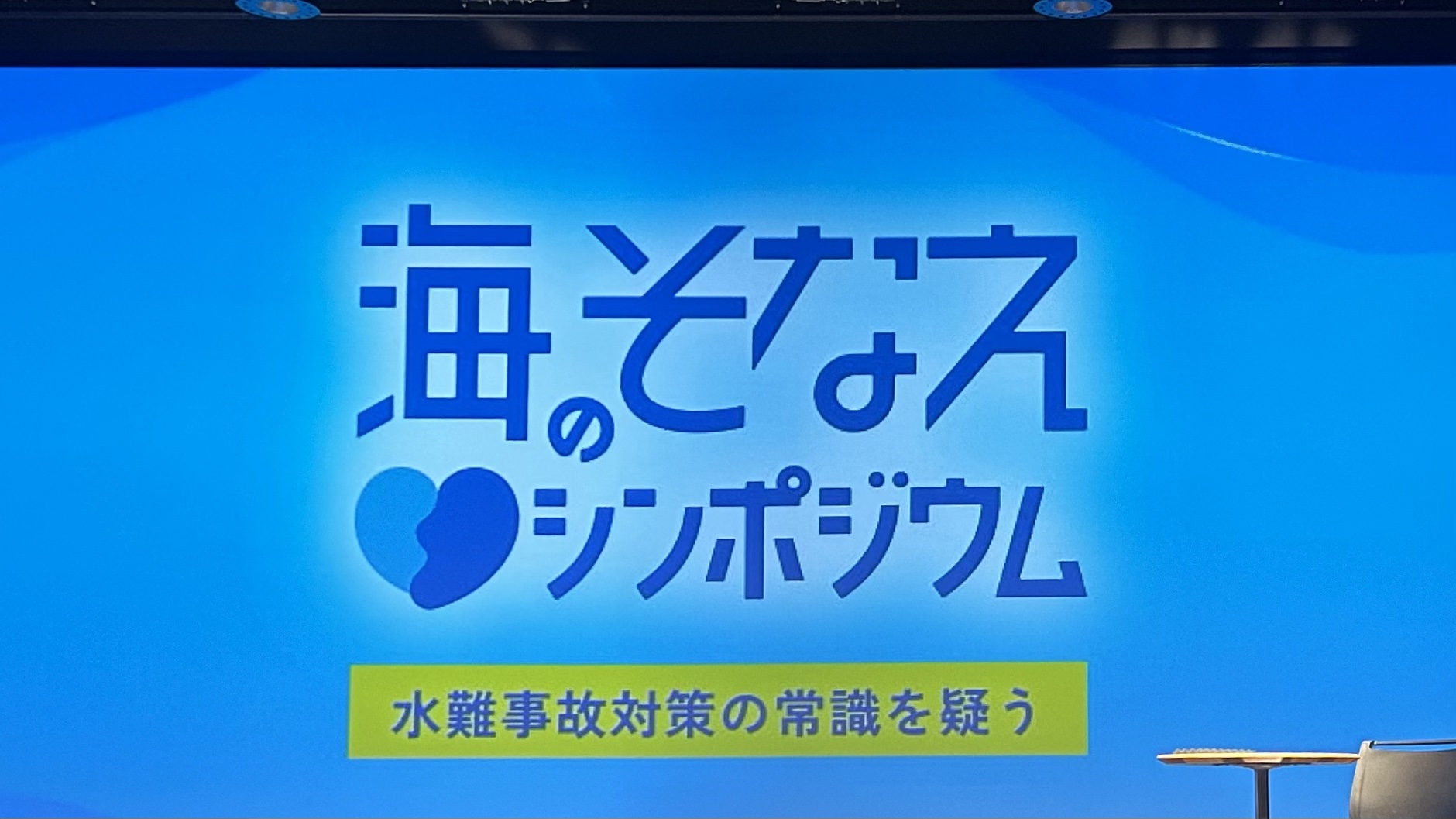
2024.06.20
海のそなえシンポジウムに参加してきました

2024.04.08
【令和6年度予算特別委員会】ボール遊びができる公園について

2024.04.05
【令和6年度予算特別委員会】不登校支援について

2024.04.05
【令和6年度予算特別委員会】一時保育など保育の受け皿について

2023.11.19
第一回品川区タウンミーティングを開催!

2023.09.26
令和5年第3回定例会 一般質問

2023.08.24
品川区議会研修会②〜道路交通法改正と電動キックボード〜

2023.08.24
